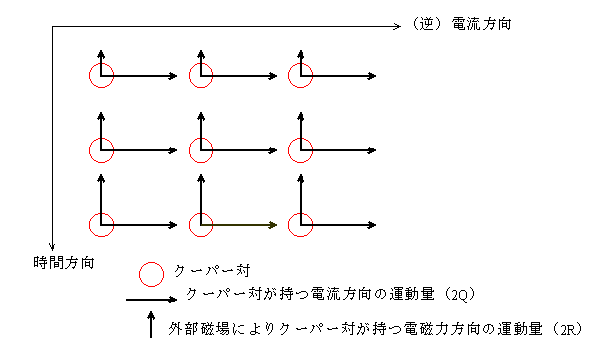|
運動量秩序の超伝導磁石への影響 久保田英文著
☆要約 超伝導状態における電子対の重心運動を考えます。超伝導状態においては、ボース・アインシュタイン凝縮と同様に、各電子対が同じ大きさの運動量に凝縮しています。そして、ある同じ大きさの運動量から別の同じ大きさの運動量に一斉に変化します。(運動量秩序) 超伝導磁石の強い磁場を作る永久電流が流れる方向においてこの運動量秩序が成立しています。また、永久電流が外部磁場による電磁力を受ける方向においても、運動量秩序が成立しています。電子対が運動量秩序に従った動きをするのに適さない不均一で移動する外部磁場を加えるとします。すると、運動量秩序の規制により、外部磁場による電磁力の力積が電子対の重心運動を動かすことができません。この力積は、電子対の重心運動を動かせないので、電子対を構成する各電子のエネルギーに転化すると考えます。そのエネルギーは具体的には、各電子の反平行運動のエネルギーや各電子の振動のエネルギーとなると考えます。電子対の重心運動を動かすことができないので、動かすことの可能な各電子の反平行運動や振動の増大に転化すると考えるのです。しかし、このエネルギーによる熱を心配する必要はありません。このエネルギーが加わっても、クーパー対のミクロな運動に不規則・乱雑性が無いことには変わりありません。クーパー対の集合である永久電流は電気抵抗ゼロで永久的に流れ続けます。抵抗ゼロであるということは、抵抗により生じる熱もゼロであるということです。クーパー対は熱には寄与しないのです。そして、これらのエネルギーは、振動自体に必要なエネルギーとして消費されたり、反平行運動を維持するためのエネルギーとして消費されたりします。その残りのエネルギーが、操作して超伝導磁石を常伝導状態に切り替えた後に、最終的に熱として放出されることがあるということです。結果として、電磁力の打消しが生じます。小さい永久磁石を超伝導磁石の近くで動かすときにも、このような現象が生じていると考えられます。 ☆序論 ボース・アインシュタイン凝縮と永久電流 超伝導状態においては、ボース・アインシュタイン凝縮が成立していると見なせます。ボース・アインシュタイン凝縮を起こしている原子の重心運動と同様に、永久電流を構成する各クーパー対の重心運動が、同じ大きさの運動量を持った秩序ある状態にあると考えられています。電子はフェルミ粒子であり、パウリの原理に従います。が、クーパー対は一種のボーズ粒子であり、同じ運動量に凝縮することが可能となるとされます。この電子対の凝縮(以下、「電子対凝縮」と略します)が、超伝導状態となった場合における電気抵抗ゼロの完全導電性を保障しています。 超伝導磁石の強い磁場を発生させる永久電流の流れる方向(以下、「電流方向」と略します)において、この永久電流を構成するクーパー対の運動量を考えます。この電流方向におけるクーパー対の運動が永久電流の実体です。基底状態にあるクーパー対1個を構成する超電子の運動量を、クーパー対を構成する超電子が反平行の運動をしているので、Pと−Pとします。そのクーパー対に電圧を加えたことにより超電子が持つ運動量をQとします。このクーパー対1個の運動量は、2Qとなります。この2Qが永久電流を運ぶことになります。 (P+Q)+(−P+Q)=2Q この永久電流に磁場を加えたとします。フレミング左手の法則によれば、外部磁場により、電流が流れる方向に垂直な方向(以下、「電磁力方向」と略します)にローレンツ力が発生します。この磁場によるローレンツ力が永久電流に働き、超電子の運動量が変化します。ローレンツ力の強さは、磁場の強さと永久電流の強さに比例します。運動量Pの超電子の運動量変化をΔPとします。すると−Pの超電子の運動量変化は−ΔPとなります。運動量Pと−Pの運動の向きが逆なので、働くローレンツ力の向きも逆となるからです。そして、運動量Qの変化をRとします。この場合のクーパー対の運動量は2Q+2Rとなります。 (P+ΔP+Q+R)+(−P−ΔP+Q+R)=2Q+2R 運動量Pと−Pの変化分はクーパー対の反平行の運動により打ち消されてしまうので、Pと−Pを変化させたローレンツ力は、クーパー対としては打ち消された格好になります。しかし、Qに対する運動量変化は残り、これが電磁力として超伝導コイルに働くと考えられます。そして、電子対凝縮が成立するためには、各電子対において、2Q+2Rの大きさが一致する必要があります。 私は、電流方向と電磁力方向の双方において、運動量秩序が成立すると考えます。運動量秩序とは、クーパー対の運動量が、ある一致した運動量から、他の一致した運動量に変化し、その変化の際にすべての対が一斉に変化することです。 まず、電流方向において、永久電流を構成するクーパー対の運動量を考えます。電流方向、電磁力方向の両方において、運動量秩序が成立しないとします。電流方向において運動量秩序が成立しないので、2Qの大きさは各電子対により異なることになります。そして、この永久電流に均一な磁場を加えたとします。均一な磁場ですので、電磁力方向の運動量2Rは、電流方向の運動量2Qの大きさに比例します。よって、この電子対の全体としての運動量2Q+2Rの大きさは、電流方向の運動量2Qの大きさに比例します。この2Qの大きさが電子対により異なると考えるので、全体としての運動量の大きさが異なることになります。これでは、電子対の全体しての運動量が一致せず、電子対凝縮が成立しなくなってしまいます。ですから、2Qの大きさは、全電子対で一致すると考えます。 次に、電磁力方向において、永久電流を構成するクーパー対の運動量を考えます。今まで、超伝導によって生じるマクロな量子効果「運動量秩序」は電流方向を念頭においていました。それを電磁力が発生する方向にも考えます。 電流方向においては運動量秩序が成立し、電磁力方向においては運動量秩序が成立しないとします。電流方向において同じ大きさの2Qの運動量を共通して持つクーパー対により構成された永久電流に、不均一な磁場を加えてみます。電流方向の運動量が一致するので、ローレンツ力の大きさは、不均一な磁場のある部分の強さに比例することになります。不均一な磁場の各部分の強さに従って、電磁力方向の運動量2Rの大きさが異なることになります。電流方向において2Qの運動量を共通して持つので、2Rの大きさに従って、電子対が持つ全体としての運動量2Q+2Rの大きさが異なることになります。これでは、電子対の全体しての運動量が一致せず、電子対凝縮が成立しなくなってしまいます。ですから、2Rの大きさは一致すると考えることになります。電磁力方向においても運動量秩序が成立すると考える必要があります。 運動量秩序を超伝導磁石における電子対の重心運動の波動で考えます。電流方向では、超伝導コイルとなる電線の全長を弦の長さとする定在波(定常波)となっていると考えます。波長の正の整数倍が弦の長さと一致します。同様に、電磁力方向では、超伝導コイルとなる電線の直径の長さを弦の長さとする定在波となっていると考えます。但し、半波長の正の整数倍が弦の長さに一致します。電流方向において電子対の重心運動が量子化されているとともに、電磁力方向においても電子対の重心運動が量子化されているので、電子対の全体としての重心運動も量子化されています。そして、電流方向に加えて電磁力方向でも電子対の重心運動の運動量が一致することにより、電子対の全体としての運動量が量子化されたある値に一致して電子対凝縮が成立すると考えるのです。 【図1】 磁場による運動量の一斉変化の例
これから、超伝導磁石に時間的に変化する外部磁場を与えた場合を考えてみます。電磁力方向にも運動量秩序が生じている結果、次のような現象が起こるのではないかと考えられます。 まず、ある時点において空間的に考えてみます。移動する磁場が、強さが異なるが一定の強さ以上の磁場を超伝導磁石各所の電子対の重心運動に与えた場合を考えます。この場合、その一定の強さ以下の揃った磁場によるローレンツ力は運動量秩序に反しないので、このローレンツ力の力積は運動量に変化しても問題はないと考えます。これに対して一定の強さを越える磁場に従ってそのままローレンツ力の力積が運動量に変化すると運動量秩序が乱されます。従って、一定の強さを越える磁場の分によるローレンツ力の力積は運動量に変化しない必要が生じると考えられます。 次に時間的変化を加えて考えてみます。ここで、磁場によるローレンツ力の影響が、超伝導磁石各所の電子対すべてにおいて、一定の時間内に一定の大きさ以上の力積に達する場合が考えられます。この力積により、超伝導磁石のそれぞれの電子対には一定の大きさ以上の運動量が生じ得ます。従って、その一定の大きさまでの揃った運動量はなんら運動量秩序に反しないので、その一定の運動量だけ電子対はそろって運動量を変化させると考えられます。 力積と力積により生じる運動量に一定の値を考えるのは電子対も量子だからです。電磁力方向において、一つの電子対の運動量がある運動量から一つ上の量子数の運動量まで変化するのに、必要な力積をkとします。一定の時間を考えるのは、その間に力積が重心運動の運動量に変化しなければ、重心運動の運動量を変化させる力積として用をなさなくなると考えるからです。この一定の時間をt秒とします。用をなさなくなった力積は、電子対の重心運動の運動量に変化せず、電子対ではなく各電子のエネルギーに転化すると考えます。そのエネルギーは具体的には、各電子の反平行運動のエネルギー、すなわち各電子の反平行運動や振動のエネルギーとなると考えます。電子対の重心運動を動かすことができないので、動かすことの可能な各電子のPや振動の増大に転化すると考えるのです。そして、これらのエネルギーは、振動自体に必要なエネルギーとして消費されたり、反平行運動を維持するためのエネルギーとして消費されたりします。その残りのエネルギーが、操作して超伝導磁石を常伝導状態に切り替えた後に、最終的に熱として放出されることがあるということです。 次に、量子数がnの状態から、n+m(nとmは正の整数)の状態に変化する場合を考えます。nからn+mの変化において、一つでもmkに満たない力積しか与えられない電子対があると運動量秩序による規制のためにn+mへの変化は生じないことになります。任意の量子数nから任意の量子数n+mの変化が生じるには、運動量秩序による規制のために、全電子対にmk以上の力積が与えられる必要があります。 一定の時間t内に、ある電子対に与えられた全電子対中で最小の力積を考えます。その力積が量子数をn+m+1まで変化させるのに必要な力積(m+1)kに満たないが、n+mまで変化させるのに必要な力積mk以上であるとします。この場合、一定の時間t内に、電子対すべてにmk以上の力積が与えられているので、全電子対の運動量が量子数n+mの状態に変化します。しかし、一定の時間t内に電子対が受ける最小の力積が、(m+1)kに満たないので、運動量秩序による規制のために、量子数n+m+1への変化は生じません。この時間t内に各電子対に与えられたmkを超える部分の力積は各電子のエネルギーに転化する可能性が生じます。次のt秒後について考えます。次のt秒の間に受けた力積と前のt秒の間に受けた力積の合計が、(m+1)k 以上に達しない電子対が存在するならば、前のt秒の間に電子対が受けたmkを超える力積は、t秒経過しているので、すべて各電子のエネルギーに転化します。ですから、2t秒の間、受けた力積が(m+1)k 以上に達しない電子対が存在するならば、時間とともに力積が累積することはなく、量子数+mの変化しか生じないことになります。従って、mkを超える力積はすべて転化してしまいますが、+mの変化分(mkの力積分)が累積して電磁力が生じえます。 以上により、運動量秩序の規制により、重心運動の運動量に変化せずに各電子のエネルギーに転化する力積が生じることがあり、その力積の分だけ、電磁力の打ち消しが生じると考えることになります。 私の理論は何ら作用・反作用の法則に反しません。超伝導磁石の電子対には作用・反作用の法則に従ってローレンツ力が作用します。その作用したローレンツ力の力積が電子対の重心運動を動かせずに、各電子のエネルギーに転化するだけなのです。 超伝導磁石よりも、非常に小さい、通常の永久磁石を用意します。この永久磁石を人間の手で超伝導磁石に近づけたり遠ざけたりしてみる実験を考えます。この場合、永久磁石には問題なく、磁力が働きます。超伝導磁石に近づけた永久磁石を動かすのに大きな力を要することはなんら問題ありません。これは運動量秩序の規制とは無関係です。では、超伝導磁石に働く力はどうでしょうか。 まず、超伝導磁石の常伝導部分が永久電流の作る磁界により磁化して、永久磁石と磁力を及ぼしあうことが考えられます。それから、この場合は低速度で移動する磁場を与えたと考えられます。永久磁石を手で近づけたり遠ざけたりすることは時間的にゆっくりしているからです。超伝導コイルを流れる永久電流を構成する電子対は時間的にあまり変化しない永久磁石の磁場の影響を受け、各電子対は一定の時間t内に一定の大きさ以上の力積を受けます。従って、運動量変化が生じ、この運動量変化が累積して超伝導磁石に電磁力が発生します。 しかし、この場合も、運動量秩序の規制は働いていると考えられます。一定の大きさを超える力積に運動量秩序の規制が働いていると考えられます。永久磁石の磁場は、超伝導磁石の一部に偏った磁場を与えます。すなわち、超伝導磁石の一部には、強い磁場を与え、他の部分には弱い磁場を与えます。この磁場にしたがって、電子対にローレンツ力が働き、電子対に力積が与えられます。超伝導磁石のある部分の電子対が受ける力積は、他の部分の電子対が受ける力積よりも、大きくなります。永久電流を構成する電子対が磁場から受けるローレンツ力の強さは磁場の強さに従って異なることになります。従って、運動量秩序による規制が働きます。運動量秩序の規制により、大きい部分の力積が電子対の重心運動を動かせない場合が生じます。この力積は、各電子のエネルギーに変化します。この分だけ電磁力の打消しが生じていると考えることになります。 この実験の場合の超伝導磁石に働く電磁力を正確に測定してみます。そして、運動量秩序の規制を考慮に入れずに計算した電磁力の理論値と比較してみます。すると、測定値の方が理論値よりも小さくなっているはずです。そして、超伝導磁石に働く電磁力が運動量秩序により小さくなっていても、気付かれにくかったのだと考えます。普通の実験において、超伝導磁石は動かない方が望ましいし、動かないように固定されているのが普通だからです。 ☆謝辞 超伝導の科学と技術の樹立に貢献された方々、特に、超伝導の原理を確立された方々に感謝の意を表します。
|