★第2章 実験方法
私の理論とそれにより起こる現象は次のようにして簡単に検証できます。超伝導磁石の上にコイルの形状に沿ってケーブルをしっかりと固定します。ケーブルは電源からループを作るようにつなぎます。ケーブルは一回巻きの常伝導電磁石となります。この超伝導磁石とケーブルからなる装置に、極めて低電圧かつ高周波数の脈流を流します。電圧は1ボルト未満とします。周波数は、波長がケーブルのループの長さと等しいものとします。そして、ケーブルのループの長さを1.6メートルとします。すると、波長は光速度を周波数で割ったものなので、
3×10の8乗÷周波数=1.6
これを解くと、周波数は、187.5メガヘルツ程度の超短波となります。電流の強さは、電圧が1ボルト未満の範囲で、徐々に強くするものとします。電圧が1ボルト以下ときわめて低いので脈流磁場の波動の力は弱く、脈流磁場よって超伝導磁石に悪影響が現れることはないと考えます。この状態で、装置の重量を計測します。
【図3】 実験図
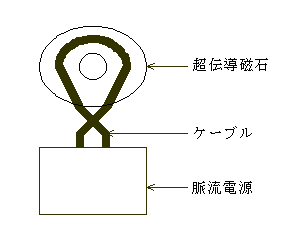
必要な物は超伝導磁石1個、ケーブル1本、高周波脈流電源1個、重量計1個。脈流電源は電源シミュレーターの機能があると良いでしょう。必要な作業はケーブルをループの形に超伝導磁石の上にしっかりと固定すること、ケーブルを電源につなぐこと、装置を重量計に乗せること、低電圧かつ高周波数の脈流を流すこと、装置の重量を計測することです。
超伝導磁石の構成するループとケーブルの構成するループの間には直接的な作用・反作用の法則が成立します。しかし、私の理論ではケーブルに流れる脈流の作る磁場が作用して超伝導コイルを流れる永久電流にローレンツ力が作用しますが、永久電流を構成する電子対を動かすことはできないと考えられます。電子対の重心運動は永久電流現象を生むマクロな量子効果「運動量秩序」に従った動きしかできないからです。運動量秩序では永久電流を構成する電子対すべての重心の運動量が一斉に同じ大きさで変化しなければならないからです。脈流波形の形状に加え脈流の作る磁場が極めて高速度で移動するため、電子対すべてに一定の時間内に一定の値以上の力積を与える磁場とはならないからです。
従って、脈流の磁場によるローレンツ力の力積を受けて電子対に生じるはずの運動量成分、すなわち電子対の電流方向に対して垂直な運動量から超伝導コイルの材料が運動エネルギーを得て生じるはずの超伝導コイルに働く電磁力が生じません。これによりケーブルに働く電磁力のみが残ることになります。
結果として、ケーブルに流した脈流が超伝導磁石の永久電流と同じ方向の場合にはケーブルから下方向の力が装置に働きます。その結果、装置の重量が増大したように計測されます。ケーブルに流した脈流が超伝導磁石の永久電流と逆方向の場合にはケーブルから上方向の力が装置に働きます。その結果、装置の重量が減少したように計測されます。
仮に、超伝導磁石の磁場の強さを5テスラ、脈流の強さを20A、ケーブルのループの長さを1.6メートルとしますと、F=BILの式により、
5×20×1.6=160
160ニュートン、すなわち約16キログラム重の重量の異常が観察できることになります。ちなみに、この場合の常伝導ループの消費電力は20A×1V=20W未満となります。
もしも、波長の長さをループの長さと一致させたときに波長の二分の一が電流ゼロである通常の脈流で効果が現れない場合は、波長のより長い部分、2/3、3/4などの部分が電流ゼロである脈流を試したいと考えます。
私の装置は産業上の利用可能性が極めて大きいものです。私の装置に重量の異常を起こさせた力を推進力・浮力・制動力として利用できます。